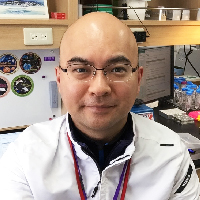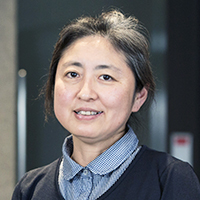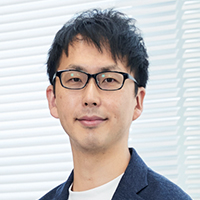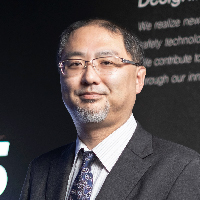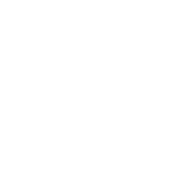
SPEAKERS登壇者
ISS・「きぼう」 利用シンポジウム 2025
2025年2月3日(月) | 10:30~18:00(予定)
弘 竜太郎
日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ戦略本部コンテンツ戦略局アナウンス部
日本テレビアナウンサーとして2018年に入社。
『news zero』『Going!Sports&News』にてスポーツキャスターを務める。2022年、兼ねてより興味のあった宇宙への挑戦として、宇宙飛行士選抜試験を受験。2023年より、日本テレビに新設された『社長室宇宙ビジネス事務局』との兼務。現在は、アナウンサーとして主にスポーツ中継に携わりながら、宇宙ビジネス事務局の一員として、テレビ×宇宙の可能性を模索中。
[コメント]
とてつもなく壮大で計り知れない宇宙に対し、時に人は、宇宙を他人事に捉えてしまいがちに。この宇宙分野の伸び代を、どこか自分事に。今後に活きるヒントに出会える1日になるよう、私も丁寧に進行させていただきます。
[登壇プログラム]
総合司会
松浦 真弓
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)理事
1986年、宇宙開発事業団(NASDA)入社。中央追跡管制所(現追跡ネットワーク技術センター)、打上げ管制部、輸送本部推進部、宇宙環境利用推進部(現有人宇宙技術部門)を歴任。JEM開発・運用プロジェクトチーム、HTVプロジェクトチームで、JEM/HTVのフライトディレクタを担当。2015年、追跡ネットワーク技術センターに異動。2016年、SSA(宇宙状況把握)システムプロジェクト、プロジェクトマネージャ。2023年、有人宇宙技術部門有人宇宙技術センター運用管制担当マネージャ兼JAXAのISSプログラムのサブマネージャ。2024年4月より現職。
[コメント]
ISSは、今もこれまで通りみなさんの頭の上を飛び続けていますが、2025年は、日本にとっては特別な年になりそうです。
まず、JAXAの大西卓哉宇宙飛行士、油井亀美也宇宙飛行士が順番にISSに搭乗し、それぞれ長期滞在の予定です。夏ごろには二人が揃って「きぼう」日本実験棟にいるところを目撃することになる、かも、知れません。
そして、更に今年、新型宇宙ステーション補給機の初号機の打ち上げが予定されています。2020年までに9回連続成功で幕を閉じた「こうのとり」の後継機です。補給機として、これまで通り確実にISSに荷物を届けますが、バージョンアップも施しており、荷物を届ける以外の任務も予定しています。詳しくはシンポジウムでご確認下さい。
このように多くのミッションが計画されているので、2025年はISSと「きぼう」から目が離せません。シンポジウムでは、そんな「きぼう」で繰り広げられる利用や実験について、多くの皆様のご意見、応援メッセージなどなどを聞けることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。
[登壇プログラム]
第1部
白川 正輝
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)有人宇宙技術部門 宇宙環境利用推進センター長
1994年4月、宇宙開発事業団(現JAXA)入社。2004-2006年、内閣府(科学技術政策担当)勤務。2022年4月より、JAXAきぼう利用センター(現:宇宙環境利用推進センター)・センター長に就任。博士(工学)
[コメント]
昨年11月に、宇宙における有人拠点等の利用を一元的に推進するため、我々の部署名がきぼう利用センターから宇宙環境利用推進センターに変わりましたが、引き続き「きぼう」を中心に利用を推進しています。「きぼう」が科学研究や技術開発の分野で優れた成果を蓄積し、地上社会や将来の日本の有人技術に不可欠な軌道上の研究開発プラットフォームとして幅広く認識されるよう、戦略的な取組みを実施したいと思います。参加者の皆さまには、是非きぼう利用の状況や取組みの最前線についてご理解いただき、引き続きご支援を頂ければ幸いです。
[登壇プログラム]
第1部、第3部
古川 聡
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 有人宇宙技術部門 宇宙飛行士グループ 技術領域上席 宇宙飛行士
1999年4月、宇宙開発事業団(現JAXA)入社。2011年、第28次/第29次長期滞在クルーとして国際宇宙ステーション(ISS)に約5ヶ月半滞在し、「きぼう」日本実験棟での実験やISS維持管理に加え、最後のスペースシャトルとなったSTS-135ミッションの支援などを実施した。2023年8月から2024年3月、クルードラゴン宇宙船運用7号機(Crew-7)Endurance号に搭乗し、第69次/第70次長期滞在クルーとしてISSに約6ヶ月半滞在。「きぼう」を含むISSにおいて、地上では得られない宇宙での微小重力環境を使って地上の生活を良くする様々な実験、さらに有人月探査やその先に向けた技術実証等を行った。
[コメント]
今年2025年に大西宇宙飛行士、油井宇宙飛行士のISS長期滞在ミッションが予定されており、応援の程よろしくお願いいたします。私自身は、ポストISSを見据えた「きぼう」の利用活動を支え、また国際宇宙探査に向けた取り組みにも貢献していきたいと考えております。
[登壇プログラム]
第1部 ※ビデオメッセージ
赤松 健
文部科学大臣政務官
[登壇プログラム]
第1部
Robyn Gatens
Director of International Space Station for Space Operations, Director of the Commercial Spaceflight Division (acting) National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Robyn Gatens is the director of the International Space Station and acting director of the Commercial Spaceflight Division within the Space Operations Mission Directorate at NASA Headquarters.
Gatens leads strategy, policy, integration, and stakeholder engagement for the space station, commercial low Earth orbit, and commercial crew programs at the agency level, including use of the station and future low Earth orbit platforms for research and technology demonstrations to support NASA's Artemis missions, and activities to secure an ongoing U.S. presence in low Earth orbit by enabling a successful, long-term private sector commercial low Earth orbit space economy. She also serves as NASA's liaison to the International Space Station National Laboratory and co-chairs the Low Earth Orbit Science and Technology Interagency Working Group.
In her 39 years at NASA, Gatens has led the development and management of life support and habitation systems for human spaceflight missions. She has also led agency strategic and budget planning to mature these habitation system technologies needed for future deep space exploration missions, using the International Space Station as a demonstration testbed.
Gatens began her NASA career in 1985 at NASA's Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama. She held various leadership positions at Marshall, including manager for the Orion spacecraft crew support and thermal systems before transferring to NASA Headquarters in Washington in 2012.
Gatens is the recipient of NASA's Outstanding Leadership and Exceptional Achievement Medals and holds a bachelor of science degree in Chemical Engineering from the Georgia Institute of Technology.
[登壇プログラム]
第1部 ※ビデオメッセージ
伊藤 徳政
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)有人宇宙技術部門新型宇宙ステーション補給機プロジェクトチームプロジェクトマネージャ
1990年4月、宇宙開発事業団(現JAXA)入社。だいち(ALOS)、しずく(GCOM-W)の開発・運用等に従事。2016年4月から新型宇宙ステーション補給機(HTV-)の開発とりまとめを担当。
[コメント]
新型宇宙ステーション補給機HTV-Xは次の2つの姿を目指します。
(1)便利で使いやすい補給船
HTV「こうのとり」から引き継ぐISS への物資輸送ミッションでは、ISSで行う実験用機器や宇宙飛行士の生活を支える荷物を届けます。よりスマートで便利な補給船となります。
(2)将来の宇宙技術を拓く宙とぶ実験の舞台
物資輸送の後、新たな技術の獲得や社会への応用につながる技術実証実験などを行うことで、我が国の課題解決やイノベーションに貢献します。
HTV-Xにご期待ください。
[登壇プログラム]
第2部
Ryan L. Prouty
Manager, ISS Research Integration Office National Aeronautics and Space Administration (NASA)
As Manager, International Space Station (ISS) Research Integration Office, Ms. Prouty is responsible for setting the overall strategy and direction of the office, ensuring alignment with the key goals of the ISS Program and the Agency. She is responsible for bringing new customers to the ISS research platform and managing the current customers' needs and expectations. In addition, she directs and controls the strategic and tactical planning and integration of research to ensure maximum utilization of the ISS. This currently requires management across eight NASA centers, the ISS National Lab management organization (CASIS), five international partners, over 15 commercial companies, and six government agencies outside of NASA. Ms. Prouty is also responsible for the day-to-day management of the Research Integration Office's resources; including 40 civil servants directly reporting to the office, $100M in budget, 110 matrixed civil servants and over 150 contractors. Additionally, she supports the agency efforts to build a low earth orbit commercial economy.
[コメント]
I am looking forward to a day of knowledge sharing and collaboration at the KIBO Symposium. Never having had the opportunity to come in person, this will be my first time to immerse myself in the whole experience with my Japanese colleagues.
[登壇プログラム]
第3部
山本 雅之
東北大学 教授 / 東北メディカル・メガバンク機構 機構長
1983年、東北大学大学院医学研究科修了(医学博士)。ノースウエスタン大学留学を経て1995年に筑波大学 先端学際領域研究センター教授就任。同大学 大学院医学研究科 研究科長を務めたのち、2007年より東北大学 医学系研究科 医化学分野 教授、副学長・医学系研究科長・医学部長を経て2012年に東北メディカル・メガバンク機構 機構長就任、現在に至る。2024年4月より東北メディカル・メガバンク機構 分子医化学分野教授。日本学術会議会員(2017年9月まで)、東北大学 ディスティングイッシュトプロフェッサー。
[コメント]
国際宇宙ステーション(ISS)・きぼう実験棟は、これまで、宇宙医学・生命科学研究の発展に大きな貢献を果たしてきました。今後も、宇宙空間を利用した新しい医学研究と革新的新産業の創出の夢を育んで、「ISS・きぼう」の利用を推進し、さらに裾野を広げていくことは重要課題です。
[登壇プログラム]
第3部
村谷 匡史
筑波大学 医学医療系教授
筑波大学卒業(2000年)、米国Cold Spring Harbor研究所、大学院にてPh.D.取得(2005年)。その後、英国Cancer Research UKロンドン研究所、A*STARシンガポールゲノム研究所を経て筑波大学に着任(2014年)。2022年より国際宇宙オミックスコンソーシアム(International Strandards for Space Omics Processing)共同代表者。
[コメント]
宇宙でヒトの体に起こる変化には、骨や筋肉の機能低下のほかにもさまざまなものがあります。地上の病院で用いられるような検査機器が使えない宇宙でこれらを調べるには、簡便で高精度な検査法が必要になります。私たちは血液サンプルを用いて体内の遺伝子や分子の状態を予測する方法を開発しており、このような技術が長期宇宙滞在中の健康管理や地上での遠隔医療にも役立つことをご紹介できればと思います。
[登壇プログラム]
第3部
有竹 浩介
第一薬科大学 薬学部 薬学科 薬品作用学分野 教授
2017年 第一薬科大学薬学部 教授
2013年 筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 分子睡眠生物学 准教授
2000年 公益財団法人 大阪バイオサイエンス研究所 分子行動生物学部門 研究員
1997年 日本シエーリング株式会社 (現バイエル薬品) 研究員
1991年 住友金属工業株式会社 (現日本製鉄) 研究員
[コメント]
遠いようで近い、国際宇宙ステーションは創薬に役立っています。宇宙では地上に比べてタンパク質の高品質な結晶化が可能となります。難病の原因となるタンパク質の結晶を解析すると、これまで治療法のなかった病気の治療薬を理論的かつ効率的に創り出すことができます。
[登壇プログラム]
第3部
黒田 有彩
宇宙タレント
兵庫県出身。
中学時代のNASA訪問で宇宙の虜に。お茶の水女子大学理学部物理学科卒業。
国の審議会委員からYoutuberまで幅広い顔を持ち、宇宙の魅力を届ける。
13年ぶりに行われたJAXA宇宙飛行士選抜試験に挑戦。
Youtube「宇宙タレント黒田有彩 --ウーチュー部--」では、1分以内で宇宙の様々なことを解説する「みんなのギモン」が人気。
[コメント]
ポストISSの時代はもう間も無く。
これまで様々な成果を生み出してきた「きぼう」の歩みに敬意を抱きますし、発想次第でいかなる可能性も拓けてくる今この瞬間に、とてもワクワクしています。
宇宙に関わるプレイヤーの方々のバックグラウンドもより多彩に。どんな話題が飛び出すのでしょうか。
会場・配信でご覧くださる皆さまの疑問を先生方にお答えいただきます!
アイデアが溢れてくるような場にできればと思います。
[登壇プログラム]
第3部 モデレーター
中須賀 真一
文部科学省 国際宇宙ステーション・国際宇宙探査小委員会 主査
1988年東京大学大学院博士課程修了、工学博士。同年、日本アイ・ビー・エム入社。1990年より東京大学講師、助教授を経て、2004年より航空宇宙工学専攻教授。日本航空宇宙学会会長、SICE、IAA等会員、IFAC元航空宇宙部会部門長。超小型人工衛星、宇宙システムの知能化・自律化、革新的宇宙システム、宇宙機の航法誘導制御等に関する研究・教育に従事。2003年の世界初のCubeSatの打ち上げ成功を含む超小型衛星16機の開発・打ち上げに成功。2012年~2022年に政府の宇宙政策委員会委員。複数の省の宇宙関連プログラムの委員長も多数務める。
[コメント]
ISSの活用はまだまだそのポテンシャルを充分に発揮しきれていないと思われ、今後、宇宙以外の分野の方も巻き込んで、新しい利用を発掘したり、利用が産業を生む道を作っていったりする必要があります。そのような試行錯誤の後に、2030年から始まる民営化宇宙ステーションでの大きな利用産業につながると期待しています。ぜひ一緒にISSや未来の宇宙ステーションの利用を考えましょう!
[登壇プログラム]
第4部
小川 志保
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)有人宇宙技術部門 事業推進部 部長
1995年から「きぼう」の利用企画・推進業務に関わり、きぼう利用戦略の策定を通じて、利用領域の重点化や民間利用拡大の仕組み作りを取り組んできた。2022年4月より現職として、部門事業を推進。
[コメント]
ゴールだった「きぼう」とISSが、地球周回活動をつなぐ乗り換え駅になりました。お弁当(技術)や飲み物(サービス)を受け取って、未来の地球周回の活動や月探査にレールが続いています。次への時刻表をお知らせできればと思います。
[登壇プログラム]
第4部、第5部
高田 正治
株式会社IHIエアロスペース 経営企画部 事業開発グループ 課長
1991年IHI入社(当時、石川島播磨重工業)以来、国際宇宙ステーションISSきぼう船外実験プラットフォームの開発を中心に、小型衛星放出機構(J-SSOD)、HISUI(ハイパースペクトルセンサ)などの開発に従事。2019年より営業部門に転籍し、商用宇宙ステーション、国際宇宙探査などの将来宇宙事業に関する企画・立案を担当。
[コメント]
ISS・きぼうの利用状況、これまでの成果、これからの展望について、多くの方々に理解して頂き、さらに興味を持って頂いて応援・期待して頂ければと思っております。
[登壇プログラム]
第4部

山本 雄大
株式会社日本低軌道社中 代表取締役社長
2013年、三井物産入社。鉱山機械の販売代理業を担当した後、海外エアライン向けの航空機エンジンのリース営業・新型エンジン開発に従事。3年半のフランス駐在を経て、2020年より宇宙事業を担当。ISS利用開拓、CLDとの提携、日本モジュール概念検討等を推進。2024年7月に低軌道専門会社である日本低軌道社中を設立し、現在出向中。
[コメント]
「モジュール、利用、物資補給、宇宙飛行士活動で構成される日本のポストISSのグランドデザインを如何に描くか?」という難しい問いに対して、日々多くの仲間と向き合っています。今回のシンポジウムを通じて、ポストISS仲間を増やしていきたいと考えています。
[登壇プログラム]
第4部、プレゼン

井上 実沙規
株式会社日本低軌道社中 利用開発部長
2015年、日本電気(株)へ入社、衛星コンポーネント開発業務の他、宇宙領域に於ける新規事業開拓業務を担当。2020年-2024年、三井物産エアロスペース(株)/三井物産(株)においてISS利用を含む宇宙利用拡大に従事。現在、日本モジュールを含む地球低軌道の経済圏構築に向けた事業開発を推進中。
[コメント]
LEOを取り巻く市場は、商業化という大きな転機を迎えており、様々なチャンスが増えていくと確信しています。同時にまだまだ課題も多いため、LEOにおけるビジネスのポテンシャルを最大限引き出すべく、皆様との連携していくことを楽しみにしております。
[登壇プログラム]
第4部、パネル
山崎 秀司
Space BD株式会社 ISS船内プラットフォーム事業ユニット 事業ユニット長
2012年、国内大手メーカーに研究職として入社。ライフサイエンス分野の新規事業を提案し、事業推進を通じて研究開発、製造、営業など幅広い業務を経験。その後、同事業リーダーとなり、プロジェクトマネジメントに従事。2022年4月、Space BD株式会社に入社。JAXA民間パートナーとして「高品質タンパク質結晶生成実験(PCG)」の営業を担当。現在はISS船内プラットフォーム事業にて、ライフサイエンスをはじめとした宇宙での事業開発およびポストISSの検討を行う。宇宙戦略基金「低軌道汎用実験システム技術」テーマの研究代表者。
[コメント]
当社は「きぼう」利用関連で船外・船内ともにJAXA民間パートナーに選定いただいている唯一の企業です。これまで、宇宙の利用開拓を推進し、実績を積んでまいりました。ポストISSおよび宇宙の商業化を見据えた更なる民需喚起に向けて、「きぼう」とその先の可能性を議論できることを楽しみにしています。
[登壇プログラム]
第4部
村上 一馬
三菱商事株式会社 宇宙航空機部 課長
総合商社にて火力発電所建設プロジェクトのプロジェクトマネジメントに従事。その後、日系通信会社にて次世代衛星通信の事業開発を推進。現職では商業宇宙ステーション事業のプロジェクトマネージャーとして事業開発に従事。
[コメント]
三菱商事はPost ISS事業者候補の一社であるStarlab社への出資を起点に、Post ISS時代における宇宙の商業化に挑戦します。宇宙事業の官から民への移管により国際競争が激化する中、日本が輝く宇宙事業、新たな時代創りを目指します。
[登壇プログラム]
第4部
佐藤 巨光
SORAxIO / 有人宇宙システム株式会社 ISS利用運用部 部長
1997年 東京大学工学系研究科航空宇宙工学専攻修了、博士号(工学)取得
同年 有人宇宙システム(株)入社
2001年 国内初の宇宙飛行士訓練インストラクタとして認定
2013年 国際宇宙ステーション(ISS)における「きぼう」の計画管理に関わる業務従事
2019年 JAMSSの新規事業開発として、独自のペイロードを開発し、ISS内での実証ミッションと宇宙環境を利用したサービス提供を実現
2022年 JEM運用・利用業務の主体であるISS利用運用部の部長職、また、LEO商業利用に関わる事業開発を担当
2024年 ポストISSでのLEO事業構想を持つ5社で、LEO市場拡大を連携して推進するため業務提携し、SORAxIO(ソラクシオ)を発足
[コメント]
民間宇宙ステーション時代の事業構想を有するJAMSSを含む国内5社は業務提携に合意し、SORAxIO(ソラクシオ)を発足させました。宇宙ビジネスへの期待が高まる中、ALL JAPANで連携することが地球低軌道の経済圏構築に向けた業界発展のために最善と考えたものです。「きぼう」で得た宇宙環境利用の知見を活用し、日本企業が世界の宇宙市場で存在感を出せるようにして参ります。
[登壇プログラム]
第4部
米津 雅史
一般社団法人クロスユー 事務局長
2022年より⼀社クロスユー事務局⻑として、東京・⽇本橋にて宇宙ビジネス拡⼤に向けたコミュニティ形成等に注⼒。⽇本の産業基盤強化のため⾃⾝でも会社経営。国⼟交通省出⾝。外務省・内閣官房・内閣府・東京都に出向経験あり。スキル:エコシステムづくり。防災・減災のための情報連携強化はライフワーク。
[コメント]
ポストISS時代を控え、宇宙ステーションの利用は今、民間企業による事業化を前提とした新たなステージへと進化しています。ビジネスの新たなフロンティアとしての利用のさらなる広がりに向けて、皆様と共に未来の可能性を探っていければと思います。本シンポジウムを通じ、産業全体としても持続可能な利用のあり方がさらに具体化する一歩となることを期待しています。
[登壇プログラム]
第4部 モデレーター
宇推くりあ
ロケット工学アイドル VTuber
2020年10月、ロケット工学アイドルとしてVTuberデビュー。日本はもちろんのこと、世界中のロケットの打ち上げ実況・解説を行う唯一無二の存在として、着々とファンを増やす。海外の配信では、英語から日本語への簡単な通訳も交えることで、英語が苦手なリスナーからも重宝されている。個人ながらH3ロケットの応援パートナーを歴任するなど、日本の宇宙開発ファンを増やす活動も精力的に行っている。アストロアーツ刊「月刊星ナビ」への寄稿を行ったり、出荷前のH-IIAロケットや人工衛星の報道公開の取材やプロモーションに当たるなど、さらに活躍の幅を広げている。
[コメント]
昨年に引き続き、このシンポジウムのアンバサダーを務めさせていただきます!「ポストISS」の時代が近づいてくる中、打ち上げの迫る新型国際宇宙ステーション補給機「HTV-X」を通してきぼうの利活用がどうなっていくのか、人類の宇宙での活動も月、そして火星へと広がっていく展望について、より多くの人に知っていただける解説をしていきたいと思います。少しでも興味があったら、是非見に来てほしいです!
[登壇プログラム]
公式アンバサダー
※プロフィールの内容は変更となることがあります